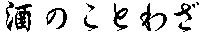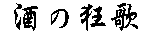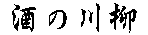
●土蜘の身振りでなめるこぼれ酒
(畳の上にこぼれた酒を土蜘のように肘を
はってなめる酒飲みで、酒好きの本性)
●きき酒をぐいぐいのんで叱られる
(酒の品質鑑定をするきき酒は口に含んで吐き出し水で口を
洗って次の酒の利き咲けをするもので飲むものではない)
●きくことに耳のいらぬは香と酒
(香は鼻で、酒は口できくものだからきく耳はいらぬという句)
●盃をさし上げて居るやかましさ
(酒をなみなみと注ごうとする者、一方はそんなに飲め
ないと辞退し、盃がだんだんと上へあがる。マァマァ
もう一こん。もうだめもうだめと騒がしい光景の句)
●盃に膳の八そう飛びをさせ
(遠い席への献盃の句)
●貴殿身どもで酒代をつきちらし
(酒代を貴殿でなしに自分が払うといい、すったもんだ
の末に割り勘で払うという田舎者を嘲った句で、
町人はみみちい割勘を軽蔑したものである)
●下戸の頭にぶっかける酒の割
(飲めない人の分にも酒代を割り当てる下戸の悲哀を詠んだ句)
●薬代を酒屋へ払う無病もの
(薬代のかわりに百薬の長である酒を飲んで
酒屋に払い自分の健康を誇る酒呑謳歌の句)
●酒屋の戸銭で叩くはなれたやつ
(拳を固めてたたいても酒屋は起きてくれない。銭でコツ
コツやると開けてくれる。銭を持っているぞとの合図)
●肌寒く行灯燗のわかれ酒
(夜ふけて火も尽き行灯で燗をしたぬるい酒で別れるというわびしい句)
●線香が消えてしまえば一人酒
(芸者や陰間をあげる時間は線香で計った。
後には揚げ代を線香代というようになった)
●女房を湯へやり亭主酒を飲む
(鬼のいぬ間に酒を飲むという酒呑みの心理を詠んだ句)
●不都合さ亭主湯あがり女房酒
(前句の反対で酒好きの女房の句)
●くせのある酒で鯨の太刀をはぎ
(鯨の太刀とは鯨の歯に銀箔を塗り刀身にかえた刀の
ことで花見酒に酔って刀を振り回すと危ないので酒癖
の悪い己を知って鯨身の刀をもっていくという句)
●悪い癖飲むと柄へ手をかける
(酔うとすぐ刀へ手をかける男のことを詠んだ句)
●生酔に明日切りやれとおさめさせ
(悪酔いして刀を抜いて男に、あした切ればよいと刀を納めさせたという句)