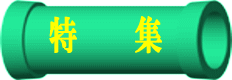
渟城幼稚園
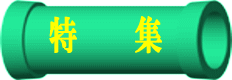
| 金銭教育研究園 |
| なんだか仰々しいタイトルがついていますが、いったい何のことでしょう? 秋田県金融広報委員会(事務局:日本銀行秋田支店内)というところが、暮らしに身近な金融に関する広報・消費者教育活動を展開しています。この教育活動の一環として「金銭教育研究校」を選定しているのですが、実は、平成14年度と15年度の2年間にわたり、渟城幼稚園がその研究園に指定されているわけです。さて、金銭教育とは何か?幼稚園児に金銭教育をして、果たして理解できるのだろうか?そして、渟城幼稚園はどんな方法で園児たちに金銭教育をするのか?順次お伝えしたいと思います。 |
今、なぜ金銭教育か
| ・・・というタイトルの小冊子を金融広報中央委員会が配布しています。この小冊子から引用させていただくと、金銭教育研究校とは、授業、勤労などの体験活動、地域活動への参加を通じて、金銭教育の具体的かつ効果的な進め方を研究する学校および幼稚園。幼稚園、小・中学校に対して都道府県金融広報委員会が委嘱し、教材や資料の配布等のサポートを行っています。ということで研究校について書かれています。さらに金融広報中央委員会の活動の中に、子どもたちに健全な金銭感覚を身につけさせる金銭教育の普及というものがあります。 さて、本題に入りましょう。以下、この小冊子からの引用(概略)となります。 子どもたちは、「もったいない」ということがわかりますか。〜子どもの意識と実態〜 日常家庭で母親が「もったいない」ということを比較的よく耳にしています。自分でもかなり使っているようです。しかし、毎日子どもたちの様子を見ている担任の先生は、「もったいない」ということが頭の中では一応わかっていても、日常の行動には結びついてはいないと指摘しています。 〜先生のことばから〜 ・「もったいない」という気持ちのない児童は、全般に乱暴で、思いやりの気持ちがないという感じがします。 ・損とか得とかにはすごく敏感ですが、心から「もったいない」ということばを使うことはあまりありません。 ・学校・家庭・社会が一体となって、物やお金や、そして人の心を大切にする教育を盛り上げる必要を感じます。 学校で落し物や忘れ物が問題になることはありませんか。 落し物の多さには目にあまるものがあるとよくいわれます。なくなっても、またすぐに買ってもらえるということでしょうか。 ある学校では、毎月第一週を記名週間とし、持ち物の記名検査、落し物調べを繰り返し行いました。記名がないと気づいたときにはすぐに記名できるように、ネームペンを教室に用意しました。名前を書いておいたために落し物が戻ってきたときには、先生がかならずよかったねとほめてやります。 〜金銭教育はなぜ必要なのですか〜 今の子どもたちは、豊かな物に囲まれて育っています。お金を手にすることの苦労も知りません。落し物をしてもとりに行こうとしない、物を大切にすることをしない。たくさんのおこづかいをもらうのが勤労の尊さがわからない、などといわれます。物が豊かであるだけに、物がお金を大切にする心を育てる金銭教育が必要といえましょう。 物やお金の働きがわかり、これを大切にすることができますか。 鉛筆や消しゴムがなければ勉強に困ることはわかっています。しかし、「物を大切にしよう」と言ったとき、具体的に何をどうすればよいか、いざとなるとよくわからないというのが実態です。 ある学校では、学習に不必要なものは学校に持ってこないこと、筆箱の中は鉛筆3本、赤鉛筆1本、消しゴム1個にしようと決めました。そして、帰りの会でその数をたしかめるようにしたところ、紛失することも少なくなり、使えなくなるまで大切に使うようになったということです。 〜金銭教育は子供たちにどのようなことを学ばせる教育ですか〜 物やお金の価値や役割についてまず理解させることです。そうすることによって、物やお金を大切にし、それを生かして使うことを学びます。そしてそこから子どもたちは、健全な金銭感覚というものを身につけ、社会人としての大切な資質をはぐくんでいきます。 ・・・その他(タイトルだけ載せます)・・・ お父さんやお母さんの仕事のたいへんなことがわかりますか。 毎月のこづかいを考えて上手に使うことができますか。 友だち同士でお金の貸し借りや食べ物をおごったりおごられたりすることはありませんか。 ・・・こういった実情から、金銭教育の必要性を訴えています。 |
渟城幼稚園での金銭教育
| さて、上記のことを踏まえて、渟城幼稚園ではどんな金銭教育をしているのでしょうか。以降は、そのことをお伝えします。 〜平成14年度秋田県金銭教育協議会発表資料から〜 金銭教育のあり方を考える 「金銭教育」という言葉を聞くと、「お金」に関する教育なのかと物的に考えがちであるが、いろいろな資料、これまでの実践例等から・・・「豊かな人間性」と「生きる力」を育てる教育であり、物を大切にする心や、働いている父母への感謝の気持ちを育む「心の教育」である・・・と受け止められる。 この教育を推し進めるには、まず定義づけ(様々な観点からみて)、あるいは仮説をたて、研究実践をしていくのが一般的だと考える。 しかし、私共は幼児期の発達の過程や、一人一人の個性・園の特色・地域性という特性を考える、前述のような進め方よりも、定義づけの前段階に掘り下げての本園の独自性を大事にした金銭教育の在り方を探ってみたいと考えた。 そこで、平成14年度は『ていようっ子にとって、金銭教育ってどんなことなのか?』というテーマで、共に園生活を営んでいる子どもたちの日常の実践なお中から、『あれ、もしかしてこんなことが金銭教育につながるのかな』という意識でこれまでの様々の実践の記録をもとに、子どもの様子を見る・知ることからスタートし、それを模索する楽しさを味わいながら、我園なりに意義づけを見出したいと考えている。 言い換えると、仮説探しと研究方法探しの段階である。
記録が物語るもの・・・ 『あれ、もしかしてこんなことが金銭教育につながるのでは』 以下に紹介する事例は、ほんの一部にすぎないが、そこに各々の教師の読み取りや解釈のズレもあることがわかる。しかし、この混とんとした話し合いの内容を無視することはできず、逆に何となく見えてきたこともある。 <3歳児> これまでの生活は、家庭は絶対の場であったが、集団という社会生活の環境に飛び込んで、様々なことに抵抗を示しつつ、しかし、ゆっくちとひとつひとつ他者からの受容で、社会性を身に付けてきまりを認識していく。まだまだ家庭のぬくもりの中にひたっていたい時期、それだけに家庭の反映も見え、影響も大きく、その日の園生活に関わってくるのも見逃せない。 ことばを徐々に知っていく時期、しかし、その使い方、表現も発達の個人差があり、思い通りに相手に伝えられないもどかしさからトラブルになってしまう。 知的発達が徐々に身についていく頃、まだまだ数・量・色などの概念形成が十分ではないものの、生活の範囲が広がるにつけ、感覚的に物には価値を表すことがあるのに気づいていく。 ひとつひとつの出来事を繰り返し繰り返し、受け止める。 ごっこ遊びに興味を示し、大人社会を真似ることからスタート。 <4歳児> 友達同士の遊びが増えてくるが、遊びのイメージが共有できずトラブルは相変わらず、そこで集団のルールを理解しようとする意識が芽生えるが、行きつ戻りつして、問題解決に向かおうとしていることが伺える。 楽しく仲間と過ごす中で、物・生物へのいつくしみも芽生え、時に興味関心からいたずらも見受けられるが、相手のいやなこと、うれしいことをわかろうとすることが体験的に身についていくようだ。 一人一人の子どもの心を支えようとする時、やはり家庭での影響や親の意識の影響が大きいことも納得する。 園では、年中という立場で大人も関わりがちだが、まだまだ教師にもゆったりと受け止めてもらいたいという時期ではないか。しかし、年少児に対しては立場をわきまえることができるのは集団の成果だと思う。 <5歳児> 気の合う仲間と目的をもって、創意工夫をしながら遊ぶ楽しさを知り、様々な社会性も広範囲にわたって身につく。したがって、きまり・約束なども自分なりに理解し、守るべきという意識が伺える。 発想も豊かになり、言語の言い回しや感性の豊かさがぐーんと目立つ頃。つぶやき「心のパッチワーク」からもその表現の豊かさに驚かされる。 物の価値・値段も把握でき、その行為に対してあこがれや興味を示す。そして、物の大切さや道徳的基盤となる判断力を守ろうとすることも十分納得できる。 身近な現象に興味・関心が深まり、気づいたり発見したりすることのおもしろさを知る。 また、自我も確立してきて、自分の思い・願いも相手にうまく伝えることは出来るが、意見や興味の違いでトラブルになることも多く。 このような意味では、子ども一人一人の家庭での子どもへ接する意識も大きく影響していることがわかる。 ていようっ子にとって金銭教育ってどんなことなのか? これまでの事例は生活のほんの一部に過ぎないのだが、この事例に対する話し合いの中から ・・・教師Aの記録・・・ 人や物を大切にする心 よいこと・悪いことの区別ができ、誘惑に負けない心 命を大切にする心 と、道徳性の芽生えを大切にする教育と、金銭教育には、共通部分があり、別々に指導できるものではないと考える。 ・・・教師Bの記録・・・ 日々、子どもが生活しているすべてが道徳性の芽生えに繋がっているように感じた。日常の保育者の声掛けや共感すること、友だちから得るもの、様々な人や教師、物と関わって知ることなど様々場面で子どもたちが学んだりすることが多々あるので、日々の生活を大切にしたい。 ・・・教師Cの記録・・・ 道徳性の発達には園ばかりでなく、家庭・地域など、子どもを取り巻く環境が大切になってくると思う。 こうして考えると「金銭教育」への手がかりは、日々の何気ない保育の中にあり、それをいかに拾うか、教師の意識に求められているような気もする。 また、見逃してはいけないことは、家庭の影響力の大きさである。やはり、一人一人の子どもの育ちを考える時、家庭との連携が重要だと考える。 言い換えると、いろいろな場面に出会ったとき、園と家庭が手に手をとって、ひとつひとつ丁寧に援助を積み重ねていくことが、子どもの心を安定させ、依存から自立へと進み、自己発揮できるのではないだろうか。そして、自分の興味・関心へと意欲的に関わって様々なものを獲得していくエネルギーが、「生きる力」であり、「豊かな心」につながると思う。 木に例えると「根」の部分にあたる幼児期に、「生きる力」をはぐくむことが幼稚園教育とすれば、現代社会に求められている「心の教育」は、金銭教育にもつながっていくと思う。 15年度はここからテーマを見い出し、更なる実践を試みたい。 おしまいに 金銭教育の在り方を探っていくうちに、いろいろなことを再認識した1年だが、楽しい心の道草もしてしまった1年であった。 それは、つぶやき集「心のパッチワーク」で母や教師の暖かい愛情があふれる会話をのぞいたり、保育者が共に生活する心地よさと楽しさがあふれる記録ノートをのぞくことで、子どもって「詩人で、哲学者で、落語家で、時に評論家だなぁ」と感心し、子どもの世界は、未来へ向かって自ら育つ明るい温かい世界であり、そこで、共に泣き、笑い、おこり、悲しむことのできる幸せをもまた、改めて感じたことである。 このような思いで、一人一人の日々のあたりまえの生活の中の何気ない事を地道に、謙虚に、丁寧に受け止め、支えていく、積み重ねの行為が子どもたちが「生きる」ための「心の貯金」となるのではないだとろうかと、感じた。 |
| NEXT → 平成15年度へ → to be continued |