現在使用中のベットラジオです。
回路はきわめて単純。
コイルは500mlのペットボトルに0.4mmエナメル線100回巻。
途中10回毎にタップ出し。
VCはおなじみ2cm角ポリバリコン。
レシーバーは国産セラミックイヤフォン。
ゲルマニウムダイオードの型番は不明。
ほとんどのパーツは15年ほど前に国分寺駅の
近くのパーツ屋さんで購入しておいたストックです。
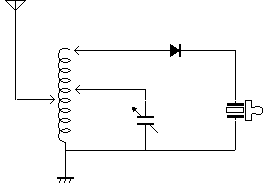
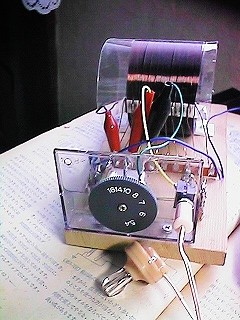
行ってます。
ロータリースイッチはもったいないので使ってません。
アンテナは屋根の上に張った約30mの銅線です。
NHK第一、第二は問題なく受信できます。
タップをうまく切り替えると
夜にはTBSやニッポン放送なども結構よく入ります。
またバリコンのタップをはずす(VC無しにする)と
短波がかなり強力に入ってきます。
タップと周波数の関係についてはまとめていません。
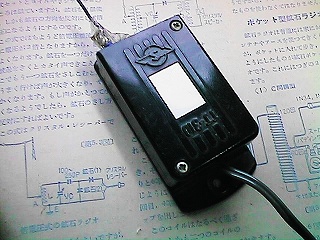
アナログ電話線に繋いだアース。
劇的な高感度を生みます。