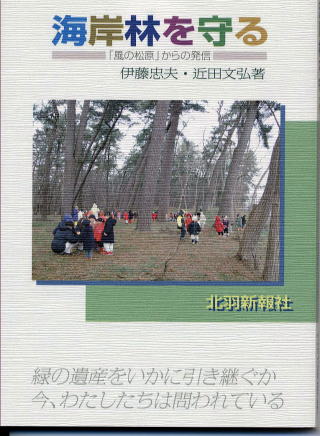『海岸林を守る』紹介と感想
作成開始04/9/6 最終更新06/1/12
今日(06年1月12日)北羽新報社に行く用事があったので1冊購入してきました。まだ入手出来ますよ。
読書をするのは、病院での待合い時間、電車の中などが多い。勤めていた頃はもっと多く本を読んだ。退職してからは<いつでも読める>という気持ちもあって、夜遅くまで読書に耽るということは少なくなった。昔は、夜、布団の中でも読んだものだったが、めがねが必要になってからは布団の中で読むのは不便だ。
さて、『海岸林を守る』の場合は、病院の待合室で読むことが多い。3回くらいは読了しているが、どんな形で書き始めればよいか、著作権侵害にならないためにはどうすべきかと考えると、読後感の筆が進まない。(「指が進まない」か?)このことは「日々の記録」11月12日の項にも書いたが、今日はとにかく書き始めよう。
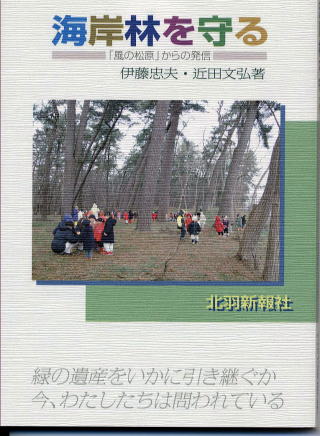 |
も く じ
刊行にあたって 北羽新報社社長 山木 泰正
はじめに
一、クロマツの分布
(1) 気候と植物の分布について
(2) 心配な広葉樹の侵入
二、日本の海岸林
(1) 失われつつある先人の遺産
(2) 今に伝わる「白砂青松」
三、クロマツ林の生育と光環境
(1) クロマツの光に対する性質 −植物は光合成で元気に−
(2) クロマツ林の更新と光環境 −複層林の造成は困難−
(3) クロマツ林の構造・推移と光環境 −ヤブに変わる可能性も−
四、クロマツ林の生育と土壌環境
(1) 森林土壌のでき方と性質 −葉が分解しやすい広葉樹−
(2) 森林の自己施肥機能 −自然肥料リサイクルで−
五、クロマツ林の生育と微生物環境
(1) 風の松原のキノコと微生物のはたらき −持ちつ持たれつの関係−
(2) 風の松原の微生物の変化とクロマツの生育−キノコが健康の指標に−
六、クロマツ林の復元
(1) 土壌と微生物環境の改善 −除伐、下刈り、植栽などで−
七、松枯れの原因と対策
(1) 松くい虫と被害の発生 −犯人と運び屋が連係プレー−
(2) 松くい虫の被害発生の仕組み −松の水分移動がストップ−
八、森林生態系と遷移
(1) 生態系のしくみと機能 −バランス良く共存し循環−
(2) 森林生態系と相互作用 −共生、寄生、競争、すみ分け−
(3) 遷 移 −人の手で純林保たれてきた−
九、風の松原の植生の現状と推移
(1) 植物の分布状況 −300を超える植物が繁茂−
(2) 白砂青松の海岸植生の消失 −ヤブに変わってもよいか−
十、森林の種類
(1) 天然林(自然林)と人工林 −天然林扱いでは守れない−
(2) 単層林と複層林、単純林と混交林(混合林) −公園的利用には人手がいる−
十一、保全・利用についての基本的な考え方
(1) 保全整備の方向 −あるべき姿を明確に−
(2) 松くい虫対策 −万全の態勢で−
(3) 利用の方向 −市民が憩い安らぐ空間に−
十二、保全・利用と官民の協力
(1) 保全・利用計画 −官民一体となった議論を−
(2) 官民の協力 −官民協力で白砂青松の再現を−
おわりに
参考文献 |
海岸林を守る
−「風の松原」からの発信−
2001年11月10日 第1刷
定価1500円(本体価格1429円)
著者: 伊藤忠夫・近田文弘
発行: 北羽新報社
〒016-0891 秋田県能代市西通町3−2
印刷: 北羽新報社印刷事業部
|
目次を紹介したので、どんな内容の本なのか、この本の全体像を理解できたことと思う。読後感を一気にまとめて書くことは難しいので、項目毎に感想を打ち込んでいきたい。
「刊行にあたって」に関する感想
|
この本を発行した北羽新報社社長 山木氏の「刊行にあたって」を読むと、本書は北羽新報紙上に平成13年1月から8月まで30回に亘って「風の松原講座」として連載されたものを、出版するにあたって再検証し、一部加筆してまとめたものだという。
最近は新聞社も自社の連載ものをwebページに掲載することが多い。昨日(04/11/11)私が「松くい虫被害地を行く」として掲載した若美町五里合海水浴場付近に気付いたのも、現在秋田魁新報夕刊に連載されている「新・奥の細道を行く」のweb版にヒントを得たものだ。
この『海岸林を行く』もweb版北羽新報に掲載していただければ、貴重な内容を広く伝えることができ、風の松原の保全保護にも役立つと思う。現在ではこの本をそのままPDFファイルにしてホームページに載せることも可能(この場合費用・日数はほとんどかからない)であり、この本の紙質・製本を簡略にして「普及版」として保全活動に利用することもできる。
風の松原が深刻な事態を迎えていることは、つい最近まであまり知られていなかったという。風の松原でマツノザイセンチュウの被害が発見されたのが平成11年、本書の発行が平成13年11月、その間僅かに3年。今年平成16年はそれから更に3年を経過している。本書で危惧された事柄が平成16年には更に進行・拡大されてはいないだろうか。
|
「はじめに」に関する感想
|
「松籟・松濤と呼ばれる音風景が失われかねない」という。私も疎開道路で育ち、南中町から能代一中に通った者として松風の音を聞いて育った。しかし、現在では松風の音は感じられない。自動車が増えて騒音が激しくなったためだろうか。朝の散歩では工場のような機械的なうなり声だけが聞こえてくる。特に23番地点から48番地点までの海に近い場所でその傾向が強い。昔とは変わった。「日本の音風景100選」にも選ばれているが、「広い松林=松籟が聞こえるはずだ」という先入観によるものではないか。インターネットで「松籟」を検索すると、このページが出てくる。環境省が作成したページだが、「重厚な松籟が楽しめる」とはどういうことか理解できない。
11月13日朝、松原を散歩しながら聞いているNHKラジオでは、ラジオ体操の次に「列島音の旅」という番組を放送している。この日は「伝統息づく金属の町」の様子を音で表現していた。ふと思ったのはこの番組で「松籟の音」を録音したことがあったか?どうか」ということだった。NHKライブラリーで風の松原の音や松籟の響きを集録しているのであれば聞いてみたいと思う。川口市に開設したNHKアーカイブスに保存されているのであれば行ってみたいものだ。
本文中にこんな一節がある。
しかし、市民には「クロマツ林がどの程度危機的なのか」、「緑がいっぱいなのに何が問題なんだろうか」とか、「風の松原の望ましい姿としてクロマツ林を回復すべきか、そのまま自然に任せて広葉樹林とした方が良いか」などということについて、認識や理解が必ずしも十分ではなく、松くい虫被害防除対策についても、観念的、感覚的な考えの人がかなり多いように感じられます。<注:以下本書からの引用部分はこのように段落を下げて、松葉色で表記します>
私も平成16年6月1日から風の松原を歩き始めた時には<クロマツ林は素晴らしい、危機的状況とは感じられない>と思っていた。それは6月から書き始めた日録「これまでの散歩の足跡」を読んでいただければわかると思う。「一般市民の方々の参考に」するためには、本書をもう一度市民の目に触れさせていただきたい。実は、私は学生時代に能代市を離れていた時も含めてずっと北羽新報を購読している。購読してはいるが、平成13年の「風の松原講座」の連載は、「そういえばそんな連載があったな」程度にしか覚えていない。
能代市民ではあったが、朝7時には出勤し、夜7時過ぎでなければ能代に帰着しない状況では、致し方がなかった。最初に目を通すのは死亡広告欄、そのほかは見出し中心、という読み方しかできなかった。
本書は、「風の松原」の自然を念頭においてまとめたものですが、全国各地の海岸林や山岳地の貴重な自然を考える上でも、大切な内容が含まれている気がします。ですから能代市の方々だけでなく、・・・・・・
その通りだと思います。だからこそ、PDFファイルとしてホームページに載せるべきだと思います。
一枚だけ試しに作成してみました。→ここをクリック
|
「一、クロマツの分布」に関する感想
気候帯や森林帯の説明があり、温帯である能代は落葉広葉樹林帯であること、そこに暖地性のクロマツ林が生育している理由がわかりました。しかし、落葉広葉樹林帯なのですから、放っておくと風の松原が広葉樹林化することももっともです。
この章の最後に「日本の海岸クロマツ林の多くが、開発や松くい虫の被害、手入れ不足だけではなく、このような広葉樹の侵入などによっても衰退し、消えようとしているのは大変残念なことです。」と書いてありますが、風の松原の場合は、特に陸上競技場から「いこいの広場」までを結ぶ高齢クロマツ林帯の西側は松くい虫よりも、「手入れ不足」とニセアカシヤによって消えようとしているのではないかと思います。 |
「二、日本海の海岸林」に関する感想
|
森林には自然林と人工林の区別があり、クロマツ林はほとんどの場合人工林であることが理解できました。我が家の窓からも遠望できる白神山地のブナ林は自然林として世界遺産にもなっているわけですが、秋田県側の藤里町奥地の場合、自然林と思われている中にも実は人工林があるのだという話も聞いたことがあります。
クロマツ海岸林の主な役割は飛砂防備と潮害防備であり、その役割を全うするためには民間所有よりも公有であることが望ましい。しかし、国有林であるために林の管理が適切に行われないことがある。国有林であるクロマツ純林に広葉樹が侵入し、クロマツ林が衰退している所がある例として、気比の松原、七里御浜の海岸林、風の松原の3つを例示している。風の松原の場合、私が散歩しながらの観察では、高齢クロマツ林(陸上競技場前の道路に面したところから大森稲荷神社の高台まで幅400メートル位の地帯)ばかりでなく、泊地に面した若いクロマツ林の部分もニセアカシアやサクラに取って代わられようとしている。
「白砂青松」という言葉がある。『風景学入門』の著者であり、土木工学者でもあった中村良夫氏は、白砂青松を「白い砂浜にクロマツがあまり密集しないで立っていて、遠くから白い砂地がクロマツの緑を透かして見えるくらいの風景」と定義していると本書では紹介している。
風の松原は「21世紀に引き継ぎたい日本の白砂青松100選」(林野庁のページよりもこちらがスマートなので載せたが、旅行会社のページなのに間違いもある)に入っている。これは朝日新聞社と「日本の松の緑を守る会」が1987年に選定したものだという。本書では、この定義を満足させる海岸林は「天の橋立」だ、「天の橋立」こそが「白砂青松」の美しい風致を備えた海岸林だという。
「天の橋立は宮津湾を横切る細長い帯のような砂地にクロマツが林を作っているのですが、大小のクロマツが、それぞれ自分の枝を十分に伸ばせるくらいの空間を持って立っています。クロマツとクロマツの間には、白い砂地が見え隠れしています。クロマツの濃い緑の枝葉を通して木漏れ日が白い砂地を照らします。あたりには、クロマツしか見られません。樹齢が百年を優に越えると思われ、直径70センチもあるクロマツの幹から、何本も太い枝が四方に伸びています。クロマツは一本一本が違った姿で立っています。(本書12ページ)
|
私は、今年になって発行された「週刊日本の樹木08 マツ」(学習研究社)を手にしています。「樹をめぐる旅」は気比の松原(けひのまつばら)です。副題は−消えゆく「白砂青松」を求めて−とついています。グラビア写真はまさに中村良夫氏の定義通りです。
同書では「日本の松原マップ」として「01風の松原」、「02高田松原」、「03松島」、「04三保の松原」、「05天橋立」、「06津田の松原」、「07虹の松原」、「08くにの松原」を紹介しています。風の松原の写真も1枚掲載していますが、例えば34番地点西側に見られる細いマツがそれこそ林立している写真です。白砂青松とはかけ離れています。
高田松原の写真も載っています。太いクロマツとアカマツが混生している風景も素晴らしいです。これだったら昨年まで友人が岩手県の高田高校に勤務していた間に行ってみるべきだったと思いました。
今度京都に行く機会があったら、日程を1日増やして、気比の松原と天の橋立を見たいと思います。 |
 |
| 34番地点海側の松林 |
「三、クロマツ林の生育と光環境」に関する感想
|
樹木には生育に光を多く必要とする陽樹(クロマツ、アカマツ、ニセアカシヤ、カスミザクラ、コナラ、ケヤキ)と比較的少ない光でも生育可能な陰樹(ヒバ、シラベ、トドマツ、ブナ、カシ類、シイ類)とがあることがわかりました。(このほか環境条件によって陰陽いずれにもなる中庸樹もある:カエデ、シナノキ、ホオノキ、ガマズミ、ニワトコなど)また、木の上の部分(樹冠層)が少ないと葉量が減少し、樹勢が衰えることもわかりました。
広葉樹がクロマツと同じ高さまで達し、枝葉がふれあうようになって、クロマツの側枝が拡張できず、樹冠幅が狭められた場合、またその可能性が大きくなった状態では、広葉樹を除伐する必要があることがわかった。また、若いクロマツ林の場合でも、木が大きくなるにつれて林が混み合い、下枝が光不足のために枯れ上がり、葉量の少ないひょろひょろした姿になって潮風や飛砂を防ぐ機能も劣ってしまう。それに対しては早めの間伐が必要だということもわかりました。
さらにクロマツを間伐した跡地にクロマツ苗を植えても、マツは多くの光量を必要とするため、まとまった広さの土地がないとクロマツは育たないことがわかりました。現在松林内にクロマツの幼木が自生していますが、あのままでは大きくはなれないのだそうです。
その上、風の松原の富栄養化という問題もあります。
現在、風の松原には広葉樹が侵入して土壌が肥沃化しつつあります。いったん広葉樹が侵入し地力が高まると、クロマツ林復元のために、皆伐による人工造林を進めようとしても、雑木林の繁茂や広葉樹の切り株からのぼう芽などのため、植栽林との間に光の競合が生じ、成林までには大変な困難が伴うことになります。(本書20ページ)
また、このまま手入れをしないでいると、クロマツ林が雑木林に変わる可能性が高いこともわかりました。樹種の陰陽性は遷移(樹種交代)との関連が深いのです。
風の松原の百年以上の高齢クロマツ林は、ほとんどが広葉樹との混交林となっており、一部にはすでに広葉樹林化している場所も見受けられます。(本書20ページ)
広葉樹が侵入したわけは、ひとつにはクロマツが生長して、林内の明るさが広葉樹の生育に都合の良い状態になったこともありますが、クロマツ林の保護下に潮風・飛砂などの厳しい環境が緩和されたことと、土壌が肥沃化したことなどがあげられます。しかし、もっとも大きい理由は、昭和30年頃まで行われていた落葉採取や草刈りなどが、ちょうど除伐や下刈りの役目を果たしていたわけですが、その後それが行われなくなり、手入れも十分ではなくなったため、広葉樹が侵入したといえます。(本書22ページ)
今後は、広葉樹を除伐しない限り、まもなくより耐陰性の強い樹種に光の競争で負け、短期間に広葉樹林になってしまうというのです。著者は、「手入れをしなければ、クロマツ林は暗くて見通しの悪い広葉樹のヤブに変わる可能性があります。」といっています。
|
「四、クロマツ林の生育と土壌環境」に関する感想
|
前章で風の松原の土壌が富栄養化していると言われたが、なぜ富栄養化したのか、その土壌のでき方についての詳しい説明が書かれていてわかりやすかった。広葉樹が育っている場所ほど、富栄養化の進行も早いので、風の松原でも紅葉が見られると喜んではいられない。広葉樹を除伐することがクロマツ林を守り育てる方法だということが理解できた。
|
「五、クロマツ林の生育と微生物環境」に関する感想
この章の最初のページは「はじめに」に関する感想のところでPDFファイルの見本として載せたが(1.風の松原のキノコと微生物のはたらき−持ちつ持たれつの関係−を書いているページ:昔は有機物が少なく土壌がやせていたのでたくさん採れたキノコが、今ではほとんど採れないことを書いている)、PDFファイルを見ることのできない人がいるかも知れないし、このページをそのまま紹介することは著作権に違反する可能性がありますので、後から削除する可能性があります。そこで、PDFファイルのページはないことにして説明します。
今年は11月はじめ、いとくスーパーで1パック1000円もしたキンダケ(シモコシ)が、昔は風の松原でいっぱい採れました。昔というのは、私が教職に就いた昭和42年、43年の頃です。朝早く松林に行くと、朝日にキンダケが金色に反射して見えたものです。そのキンダケが採れなくなった原因がクロマツの樹勢の衰えと関係しているということがこの本で初めてわかりました。
また、クロマツの根にとりつく根菌は、クロマツから炭水化物を分けてもらい、代わりにリンやミネラルを宿主のクロマツに供給する共生関係にあります。
それに対して、ニセアカシヤの根にとりつく根粒菌は空中にあるチッソを固定して宿主のニセアカシヤに供給します。ニセアカシヤは土地を肥やす肥料木と呼ばれているのだそうです。やせた土地に適しているクロマツと、土地を富栄養化するニセアカシヤとは全く反対の性質だということがわかりました。
クロマツの根にとりつく菌糸はクロマツの細根の表面をおおい、それがバリアーとなって病原菌の侵入を防いだり、乾燥・冷害・高温に対する抵抗力を高めていますが、土壌の富栄養化にりクロマツに共生していた根菌根が消えてしまい、そのためにクロマツの樹勢が衰えるのだということでした。
ニセアカシヤは根粒菌との共生で空中チッソを固定しますが、クロマツの菌根菌は土壌中のチッソが多すぎると消えてしまうのだそうです。
11月14日日曜日にロケットセンター付近まで行ってきました。この様子は「22番地点〜港湾道路」というページに載せたので、そちらを見ていただきたい。私がいつも散歩している場所(私が作成した地図に載っているジョギングコース)は後谷地国有林の中だが、こちらは国有林ではなく県有林だ。まだクロマツが若いのでキノコも採れるらしい。「らしい」というのは私は30年近くもキノコ採りをしたことがないからだ。
右の写真上に写っている道路は同じ幅で4キロも続き、その先は道幅が狭くなるが、又2キロも続いている。その林内のところどころに自動車が止まっている。この写真も左側100m位の間に3〜4台が停車している。それだけでなく、3枚目の写真のような自転車で港湾道路から2キロも入った地点まで来ている人もいるのだ。
この自転車の持ち主は11時半頃までキノコを採ってから帰って行ったが、70代後半と思われるおばあさんだった。
キノコ採りの人たちが小型の熊手のような道具(写真下)で、キノコを探すのだが、松葉の下になっているキノコも多いので、ついには2枚目の写真のように松葉を耕したような形になってしまう。このような状態の場所が、写真上の右側(西側=海側)ずーっと遠くまで続いていると思って間違いない。(「松葉かき」と同じ効果?)
先ほどニセアカシヤの害について書いたが、ここの松林と泊地近くの松林は同じような太さの松だが、泊地近くの松林がニセアカシヤに覆われるようになっているのに、ここにはニセアカシヤが生えていないことはクロマツの為にもキノコのためにも幸いしていると思った。 |
 |
 |
 |
 |
「六、クロマツ林の復元」に関する感想
「七、松枯れの原因と対策」に関する感想
「八、森林生態系と遷移」に関する感想
「九、風の松原の植生の現状と推移」に関する感想
「十、森林の種類」に関する感想
「十一、保全・利用についての基本的な考え方」に関する感想
「十二、保全・利用と官民の協力」に関する感想
その他感じたこと
・本書の紙質・製本について
本書は、カラー写真・図版を70枚ほど掲載することを考慮したためか、厚手の上質な紙を使用している。そのため、何度もページをめくっていると、紙が1枚ずつ綴じしろから切れてしまう。私は比較的丁寧に本書を利用しているつもりだが、目次の部分は既に1枚ずつバラバラ(barabara)になってしまった。これは紙が厚いための弊害だと思う。
疑問点として残ったこと
1.カラーページの「写真−2」に風の松原が示されているが、ここには大開浜国有林が含まれていない。