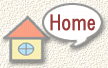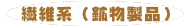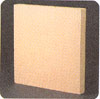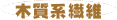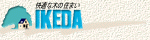 |
 |
| 快適な住まいを作るには断熱材が重要建材になりそうです。その断熱材にはこんなメリットが
あります。 |
| 快適で健康的なマイホームライフ |
| 断熱材を使用することで、年間を通して快適な室温を保ちやすくします。お年寄りや子供たちにも
優しい快適なマイホームライフが実現します。 |
| マイホームが長持ち |
| 冬場の室内外の温度差で、結露しやすくなると壁紙が剥がれたり、カビの発生の原因になります。
しかし断熱材を使用することで、外の冷気を遮断し、結露しにくいマイホームが実現できます。 |
| 省エネ効果で経済的にもお徳 |
| 断熱材を使用した住宅の冷暖房をみた場合、十分遮断された家では、平均して暖房で約半分、冷房で
約1/3の費用を減らすことができます。 |
| 地球温暖化防止への貢献 |
| 冷暖房費が少なくなるということは、それだけ省エネ効果があるということで、地球の資源保護につながります。
また、温暖化の原因である二酸化炭素の発生量も減らすことができます。 |
|
では、どんな断熱材を選んだらよいのでしょう? まずは断熱材の種類から見ていきましょう。 |
|||||||||||
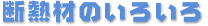 |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
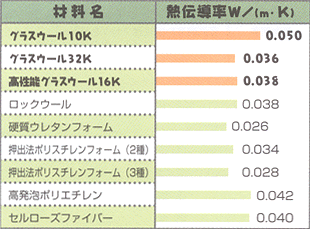 |
これだけいろんな種類があるとどれを使うのがいいのかわかりませんね。
断熱性能の高い断熱材はどれなのでしょう? 左図の熱伝導率の表を見てみましょう。 数値が低い方が熱を伝えにくいということになります。左図では、硬質ウレタンフォーム などの発砲プラスチック系が熱を伝えにくくなっています。 でも・・・・ |
 |
||||||||||||||
| 断熱材の性能を比較する場合は熱抵抗という値を見る必要があるんです。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
一般的に高性能といわれる住宅で使われている断熱材の性能を比較してみましょう。 |
||||||||||||||
|
左記のようにグラスウールの方が、熱抵抗値において高い数値を示しており、
断熱性能に優れているということがわかります。 断熱材の厚みが、そのまま断熱性能に比例するといっても過言ではありません。 ・・・「でも、断熱材を厚くしている分、コストが高くつくのではないか・・・」と思いませんか?? 
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
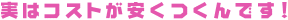 全く逆で、同じ性能でこんなにローコストなんですよ。 40坪程度の住宅を想定して、断熱性能(次世代省エネルギー基準レベル)が全く同じになるような 使用でコストを計算してみると右図のようになります。 グラスウールの充填断熱工法は、コストパフォーマンスに優れているんです。 |
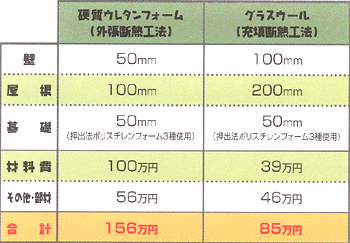 |
|||||||||||||
| "㈱MAG 新築さん一家の正しい断熱材選び"より |
|
|
このコラムは毎週木曜日更新し、数回にわたって連載していきます。 次回は断熱材の選び方 その2です。 お楽しみに! |